GA4の拡張計測機能とは?自動収集イベントとの違いを整理する
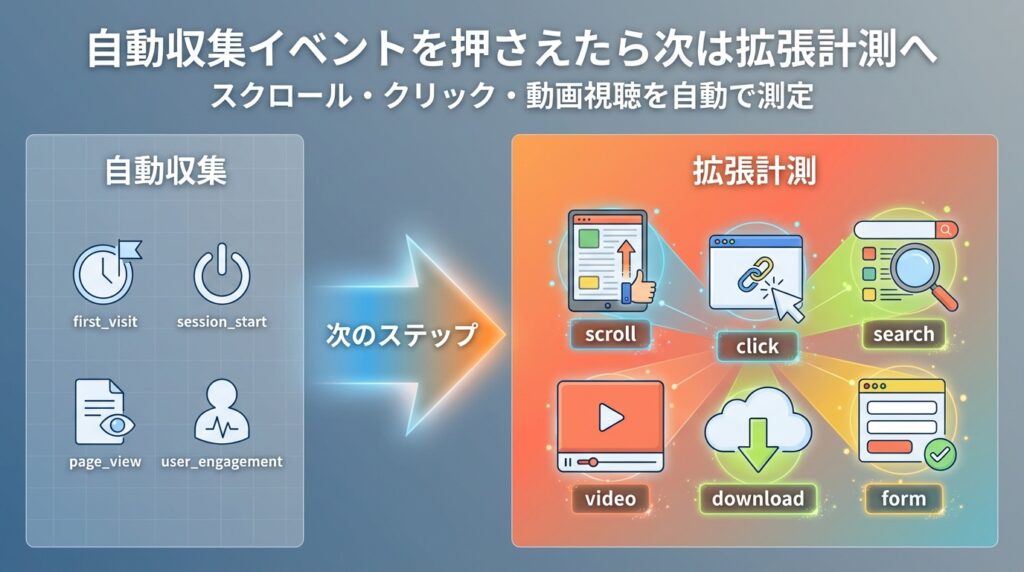
GA4を触り始めると、だいたい最初にこう思います。
- PV(ページビュー)は見れている
- でも「どこまで読まれた?」「どこをクリックされた?」が分からない
- それを取るにはGTMで難しい設定が必要そうで不安
結論から言うと、その悩みの多くは GA4の「拡張計測(Enhanced measurement)」 で解決できます。
拡張計測は、難しい設定をしなくても、スクロール/クリック/検索/動画/DL といった行動を「イベント」として自動で取れる機能です。
この記事では、拡張計測の正体と、自動収集イベントとの違いを整理し、あなたのサイトで「何をONにすべきか」を迷わず判断できる状態を目指します。
1この記事でわかること
この記事で持ち帰ってほしい結論は3つです。
- 拡張計測は「追加で取れる行動ログ」をスイッチで増やす機能
- 自動収集イベントは“土台”、拡張計測は“観察ポイントの追加”
- まずはONで可視化 → 次に“意味のある指標”に整える(設計が大事)
「拡張計測をONにしたら何が増えるの?」「自動収集と何が違うの?」を、今日ここでスッキリさせましょう。
2 そもそもGA4は「イベントで世界を見ている」

GA4の一番大事な考え方はこれです。
GA4では、ユーザーの行動はすべて「イベント」として記録される
ページを見た(PV)も、スクロールしたも、クリックしたも、動画を見たも、全部イベントです。
だからGA4を理解するコツは、「指標を覚える」より先に、どんなイベントが、どんなルールで記録されているかを掴むことです。
2-1 イベントには4種類ある(全体地図)
GA4のイベントは、ざっくり4種類に分かれます。
- 自動収集イベント:最初から必ず取れる基本ログ
- 拡張計測イベント:スイッチONで追加で取れる行動ログ(今回の主役)
- 推奨イベント:Googleが「こういう命名で取ると良い」と勧めるイベント
- カスタムイベント:あなたのビジネスに合わせて自由に作るイベント
今回扱うのは、2つ目の 拡張計測イベント です。
3 拡張計測機能とは何か(データストリームのトグル)
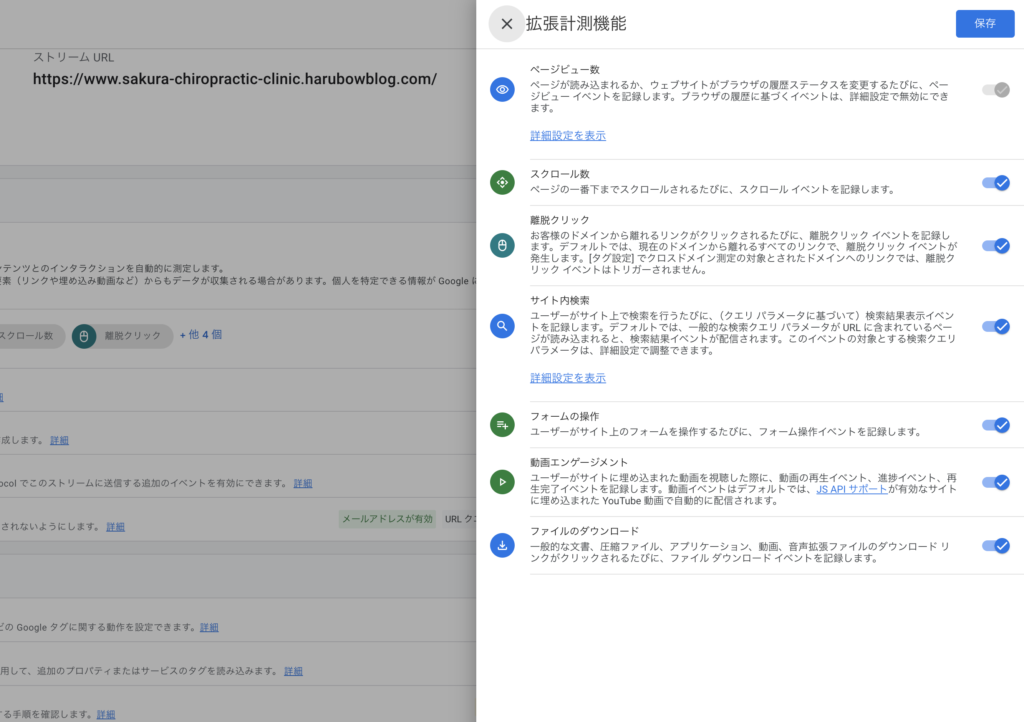
拡張計測は一言で言うと、
GA4が“よくある行動”を、設定少なくイベント化してくれる機能
です。
3-1 どこで設定する?(最短導線)
設定場所はここです。
- 管理(Admin)
→ データ ストリーム
→ Web(対象のストリーム)
→ 拡張計測機能(トグル)
ここでON/OFFできるのが、いわゆる「拡張計測」です。
3-2 トグルON=イベントが自動で発火する
拡張計測をONにすると、あなたがサイトを操作したときに、GA4が自動でイベントを送るようになります。
- ある程度スクロールしたら「スクロールイベント」
- 外部リンクをクリックしたら「クリックイベント」
- ファイルをダウンロードしたら「DLイベント」
- 検索したら「検索イベント」
- 動画を見たら「動画イベント」
つまり、イベントが増える=見える世界が増える ということです。
3-3 拡張計測が面倒を見てくれる範囲(できること/できないこと)
拡張計測は便利ですが、万能ではありません。
できること
- ありがちな行動(スクロール、外部クリック、検索、DL、動画)を自動記録する
できないこと
- ビジネスの成果を定義する(例:申込完了、予約完了、購入完了など)
成果を追いたい場合は、推奨イベントやカスタムイベント(多くはGTM)も必要になります。
ただし、最初から全部やろうとすると挫折しやすいので、まずは拡張計測で「見える状態」を作るのが正攻法です。
4 自動収集イベントとの違い(必ず取れる vs 自分でON/OFF)
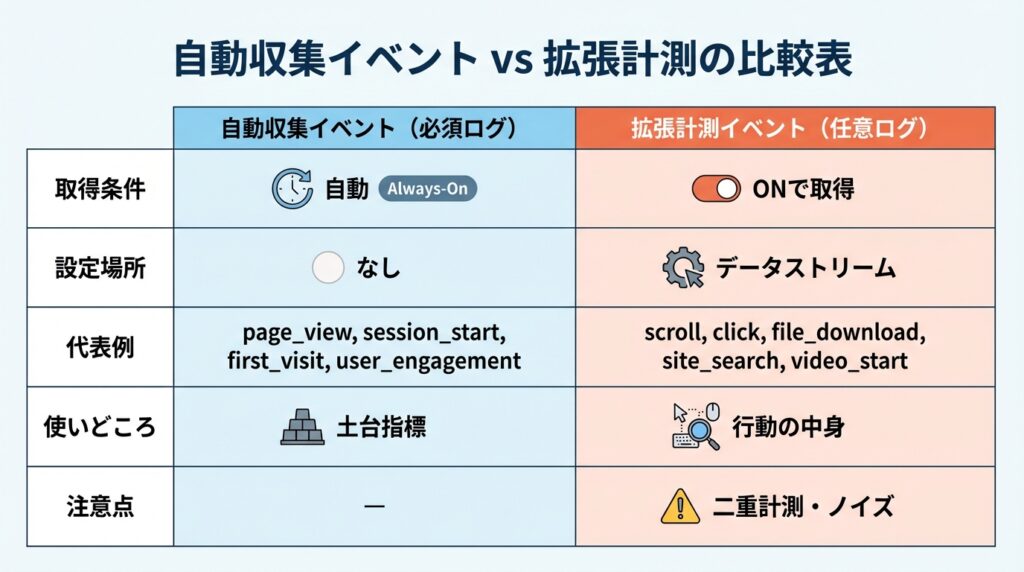
ここが一番大事です。
言い換えると、“土台”と“追加観察”の違いです。
4-1 自動収集イベントは“最低限の心拍数”(基本ログ)
自動収集イベントは、基本的に 必ず取れます。
代表例は、あなたがこれまで学んできた4兄弟です。
- first_visit:初回訪問(新規ユーザー)
- session_start:セッション開始(訪問の単位)
- page_view:ページ表示(PVの正体)
- user_engagement:エンゲージメント(滞在・アクティブの手がかり)
これは、GA4の「最低限の呼吸」みたいなものです。
これがないと分析が始まりません。
4-2 拡張計測は“診察項目を増やす”(任意ログ)
拡張計測は、あなたが ONにすると取れる イベントです。
- スクロールしたか
- 外部リンクを押したか
- 検索したか
- 動画をどこまで見たか
- ファイルをDLしたか
つまり、**自動収集だけだと分からない「行動の中身」**が見えてきます。
4-3 現場で多い誤解:「PVが取れてるからクリックも取れてる」
これは誤解です。
- PV(page_view)は、ページが表示されたログ
- クリックは、別の行動ログ
PVが見えていても、クリックやスクロールは見えません。
だから拡張計測が必要になります。
4-4 判断軸:まず“取れる状態”→次に“意味ある指標”へ
最初はこう考えると迷いません。
- まずは拡張計測をONにして、行動が取れる状態を作る
- 次に、重要なイベントだけをKPI候補として“意味づけ”する
「全部ON=全部見る」ではなく、
「全部取る=あとで必要なものを選べる」くらいの感覚がちょうどいいです。
5 拡張計測でできるようになること(全体像)
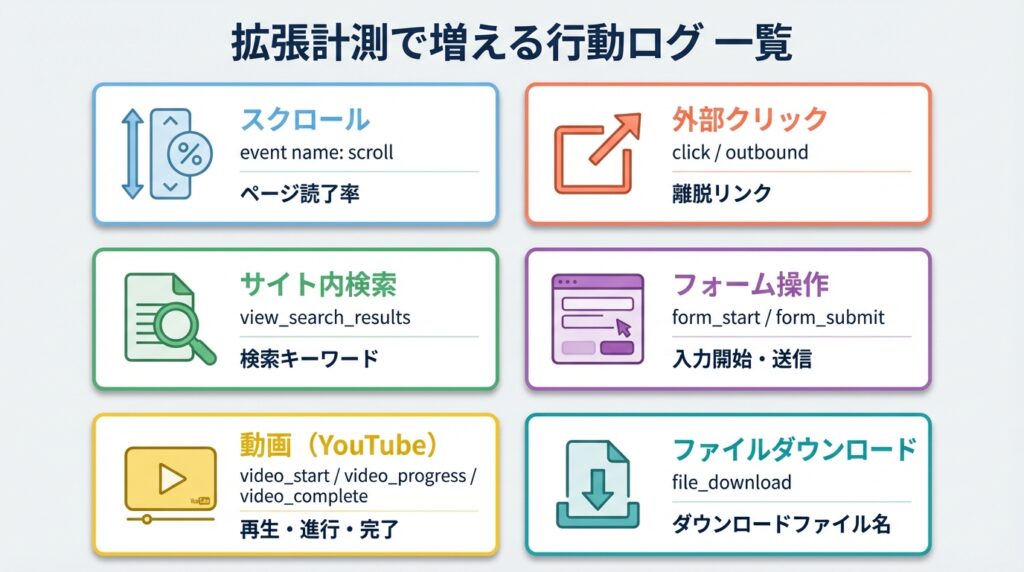
拡張計測で代表的に取れる行動は、次の6つです。
- スクロール
- 外部クリック(離脱クリック)
- サイト内検索
- フォーム関連の自動計測(環境により見え方が異なる)
- 動画エンゲージメント(YouTube)
- ファイルのダウンロード
ここでは「何が分かるか」を1行で整理しておきます。
スクロール:読了の近似ができる
「最後まで読まれている記事か?」を判断する手がかりになります。
PVだけだと、流し見なのか熟読なのか分かりません。
外部クリック:送客の把握ができる
外部サービス(予約、購入、別サイト)への遷移が多いサイトでは特に重要です。
サイト内検索:ユーザーの“探し物”が分かる
検索語はそのまま「足りないコンテンツ」や「ニーズ」です。
ブログのネタにも直結します。
動画:コンテンツ価値の把握ができる
「動画が見られているか」「何%まで再生されたか」が分かると、LP改善に効きます。
DL:資料価値の把握ができる
PDFや資料を配っている場合、DLは“成果に近い行動”になりやすいです。
どこで見られる?(迷わない導線)
まずはここで確認すればOKです。
- レポート → エンゲージメント → イベント
慣れてきたら「探索(Explorations)」で深掘りします(シリーズ後半で扱うと理解が進みます)。
6 どんなサイトで特に効果が大きいか(ブログ/LP/予約サイトなど)
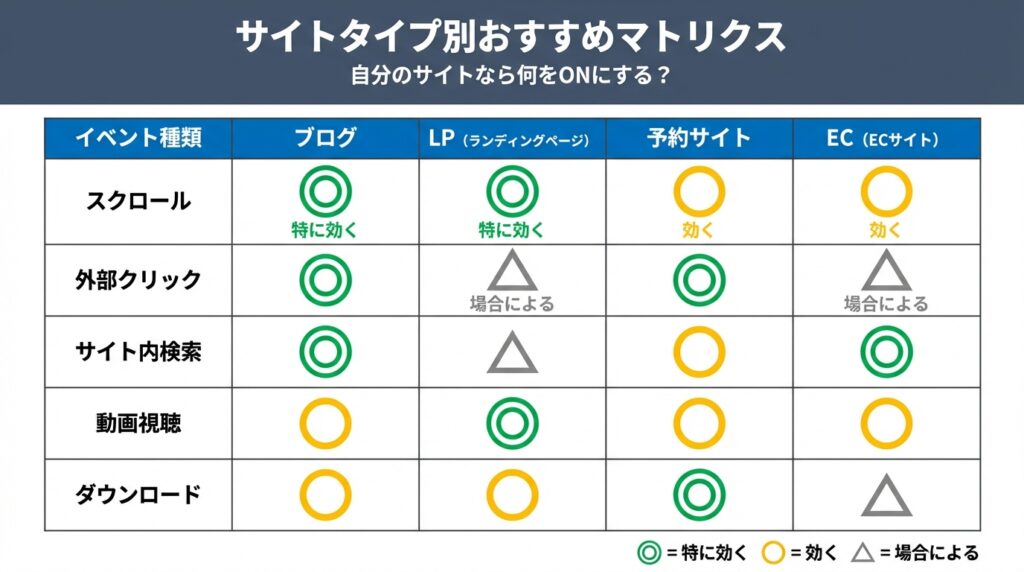
拡張計測が特に効くサイトタイプを整理します。
6-1 ブログ・メディア:読まれ方とニーズが見える
- スクロールで「読了に近い行動」が見える
- 外部リンクで「送客できている記事」が分かる
- サイト内検索で「探されているテーマ」が分かる
ブログはPVだけだと改善が止まりやすいので、拡張計測の恩恵が大きいです。
6-2 LP:1ページ勝負の改善に刺さる
LPはページ数が少ないので、
- どこまでスクロールされたか
- CTAが押されたか(外部遷移やクリック)
- 動画が見られているか
が、そのまま改善仮説になります。
6-3 予約サイト・店舗サイト:離脱の手がかりが増える
例えば整体院や美容室だと、
- 外部予約サービスへ飛ぶクリック
- メニュー詳細の閲覧
- FAQの閲覧(スクロール)
などが、来院意欲の温度感を推測する材料になります。
6-4 EC:本命は推奨イベント、拡張計測は補助
ECは「購入」まで追うなら推奨イベント(ecommerce)が本命です。
ただし、拡張計測で
- 送客
- 検索
- 動画
などを補助的に見ることはできます。
ただしイベントが増えすぎるとノイズになりやすいので、設計が重要です。
7 まず何をONにする?おすすめ初期設定(チェックリスト)
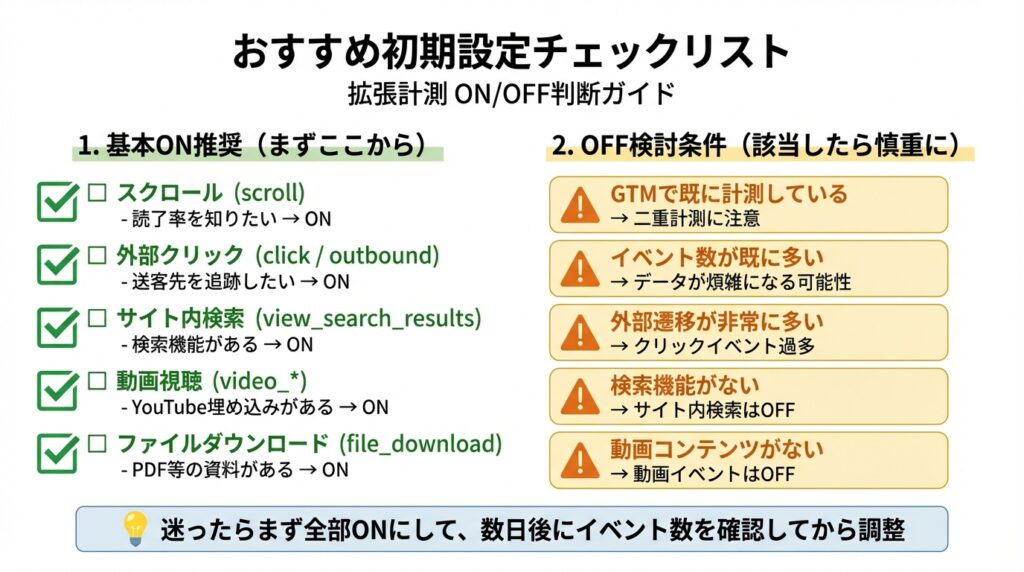
ここでは、実務で迷わないための「初期設定方針」を置いておきます。
7-1 基本セット(多くのブログ/小規模サイト向け)
- スクロール:ON
- 外部クリック:ON
- サイト内検索:検索機能があるならON
- DL:資料やPDFがあるならON
- 動画:YouTube埋め込みがあるならON
まずはこれで「読まれ方/送客/ニーズ/価値ある行動」が見えるようになります。
7-2 場合によってはOFF検討(トラブル回避)
以下に当てはまるなら、一部はOFFや設計変更を検討します。
- すでにGTMで高度なクリック計測をしていて 二重計測になる
- イベントが増えすぎて 分析が破綻する
- 外部クリックが多く、クリックが“成果”として誤解されやすい(レポートの読み間違いが起きる)
「取れること」と「使えること」は別なので、目的に合わせて整理するのがコツです。
8 落とし穴(拡張計測あるある5選)
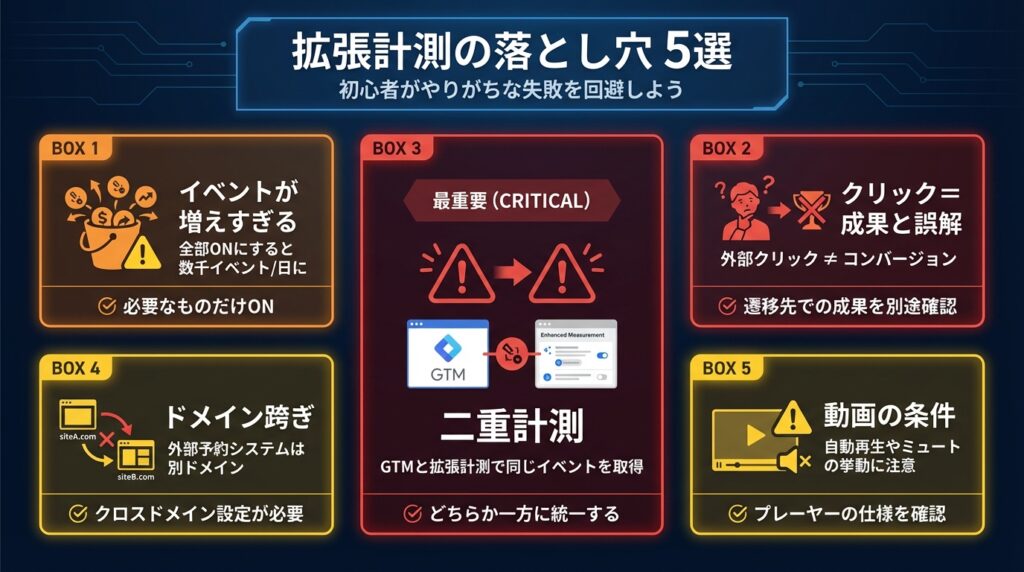
拡張計測でよく起こる失敗を先に潰しておきます。
1)イベントが増えすぎて、何を見ればいいか分からなくなる
→ 対策:見るイベントをKPI候補に絞る(全部見ない)
2)クリックを“成果”と勘違いして意思決定がズレる
→ クリックは「行動」であって「成果(CV)」とは限りません。
成果にしたいなら、CV定義(重要イベント)を別途作る必要があります。
3)拡張計測×GTMで二重計測になる
→ 対策:どっちで取るか方針を決める(基本は片方に寄せる)
4)外部遷移が多いサイトは、ドメイン跨ぎの設計も必要
→ 予約や購入が別ドメインなら、クリック計測だけで満足しない(成果まで追う設計が必要)
5)動画計測には条件がある
→ 例えばYouTube埋め込みなど条件が絡むので、詳細は動画回で整理すると理解が確実です。
9 最短で動作確認する方法(5分で確認)
設定したら「取れているか」を確認しましょう。
これをやらないと、いつまでも不安が残ります。
9-1 確認フロー(おすすめ)
- 自分のサイトで実際に操作する
- スクロールする
- 外部リンクをクリックする
- 検索する(検索機能があれば)
- PDFなどをDLする
- 動画を再生する - GA4でイベントが見えるか確認
- レポート → エンゲージメント → イベント
- 可能なら DebugView(デバッグ)も見る
ここでイベントが見えたら、「設定は動いている」と判断できます。
9-2 確認できたら次にやること
- 重要そうなイベントを3つだけ選ぶ(KPI候補)
- “成果”に近いもの(DL、予約遷移クリックなど)を仮で重要視する
- 次回以降で、イベント別に「どう読むか」を深掘りする
ChatGPT先生と学ぶ「拡張計測」ミニノック(理解チェック)
Q1:ブログで“読まれている記事”を見たい。まずONにするのは?
答え:スクロール(+可能なら動画や検索も)
PVだけでは「読んだか」が分からないため、スクロール計測が効きます。
Q2:GTMでクリック計測済み。拡張計測のクリックもONだと何が起きる?
答え:二重計測のリスクがある
同じクリックを2系統で送ってしまうと、イベントが増えて混乱しやすく、数字の信用が落ちます。
Q3:LPで予約ボタンが別ドメインに飛ぶ。拡張計測だけで十分?
答え:十分ではないことが多い
拡張計測で「クリック」は取れても、別ドメイン側の「予約完了」まで追えない場合があります。成果まで追うなら、ドメイン跨ぎの設計や、別側の計測整備が必要です。
まとめ(今日の結論)
- 拡張計測=データストリームのトグルで増やせる行動ログ
- 自動収集は土台、拡張計測は観察ポイントの追加
- まずはONで可視化 → 次に“意味のある指標”に整える
次回予告:まずは「スクロール計測」から使いこなす
次回は、拡張計測の中でも特に使いどころが多い スクロール計測を深掘りします。
- 「どこまで読まれたか」をどう解釈する?
- PVが多いのに成果が出ない記事は、スクロールで見抜ける?
- ブログ改善の“最初の一手”としてどう使う?
拡張計測は、ONにするだけで終わりではなく、“読める”ようになって初めて武器になります。次回で一気に実務に落とし込みましょう